生産性を向上させることがどれくらいとれ暗い経営に貢献するの?
新商品開発やマーケティング、営業に力入れて、販売増やしたりする方が儲かるんちゃうの?
みたいなこと考えたことありませんか?
「工場の生産性を改善」工場を経営する人で、この言葉を経営方針などに入れない経営者はほとんどいいないかと思います
その目的は、「効率よく生産して人件費を減らすこと」になる場合が一般的です
でも、冒頭のようなこと悩むんですよね
実際利益を増やす、会社の業績を向上させようと思えば、新商品や、マーケティング、販売チャネル開発し、販売を増やせば生産性の改善より成果は出やすいです
ですので、現実には現場改善より、こちらを優先する経営者も多いように思います
それでも、現場改善を行い、生産性を向上させることを必要と感じて取り組んできました
生産性の改善の目的は、人件費だけではなく
「製造の現場改善を行えば、販売も伸び、資金も増え、最終的には会社全体の組織能力の向上につながり、会社の業績全体が良くなる」
と考えてきたからです
工場経営者としての悩み
海外生産拠点の経営者になりたての時の悩みの一つとして、「工場のあらゆるロスを減らして、生産性を改善することの意味をどう考えるか」がありました。
「工場を経営するんやから当たり前やろ」なんですが、生産性を改善して人件費を下げるより、販売を伸ばす方が利益は増えます
限りある経営資源(特に人)効率的に使うには、経営者として「販売」に目が行ってしまいます
そのために、新商品開発、マーケティング、販売チャネル開発等、経営資源を集中させるべきとも考えたります
でも世界のトヨタは徹底的な現場改善の成果で結果を出している
「トヨタの業績の中で現場改善の成果はどれくらい占めているだろう?」
という疑問も結構ありました
こんなことを考える方が変人なのかもしれません
周りの経営者を見た時、「生産性改善/現場改善」と口では言うものの、本気で取り組んでいないような工場もたくさんありました
実際、ロスのある工場で、改善して一人作業者減らせたところで、人件費への影響は大きくはありません
特に人件費の安いアジアの工場ではそうです
また、少々効率悪くても、残業して工場動かせば数量は確保できます
むしろアジアの工場は残業や休日出勤が減ると収入が減って会社を辞めていきます
経営者として、「生産現場の改善より優先することあるんちゃうの」最初のころはけっこう考えていました
そんなことを考えながらも、
「工場のくせにロスが発生してるはよくない」
「実際トヨタはそれで世界を制している」
と考えて、少し心にひっかるものを感じながらも、コンサルにも協力いただき、現場改善による生産性の向上の活動を常に優先高く取り組んできました
工場の生産性改善の取り組みを優先に取り組んだ理由
上記なような疑問を持ちながらも、現場改善による工場の生産性向上を経営者として優先しました
その理由ですが、先に述べた「工場のくせにロスが発生してるはよくない」「実際トヨタはそれで世界を制している」 以外で、
①販売を伸ばすための方策(新商品、マーケティング、チャネル開発等)は、別に経営TOPが言わなくても実行する=専門の部署がある
さらに、成果が見えやすいので、社員は積極的に実施する
②製造は、その役割の主なものが生産すること。だから量を優先して「改善して効率よく生産する」という考えが自発的に生まれにくい
という理由から、現場改善の取り組みは積極的に実施さていない現実を感じたからです
もう少し詳しく話しますと、少し極端ですが、製造現場は決められた生産台数を生産しきれば、ある意味合格
少々効率悪くても、数量確保できれば、問題にされることは少ない
(少なくとも私が担当した工場は、赴任着後そんな工場でした)
ですので、トラブル発生時にはとっても動きが良いにもかかわらず、効率の悪さ、例えば、二人でできる作業を三人かけてるとか、こんな現実は放置されやすいです
ということで、これっておかしいよな、と考え優先的に取り組みようにしたわけです
経営トップが言わないと、なかなか自発的に改善しないからです
トヨタのように、改善することが会社の文化になっていれば問題ないのですが、そうなっていない工場もまだまだあるってことです
しかし、冒頭に述べたような、改善が経営にどれだけ貢献するのだあろう?って悩みはずっともっていました
悩んでいきついた結果
悩みながら、生産数量を追っかけるので精一杯の現場を鼓舞しながら、改善活動を常にさせてきました
その間、いろんな人の話を聞き、結局「現場改善をし生産性を上がる目的=効果」として、下記の考えに行きつきました
①生産性を上げ、人件費を下げる(一番わかりやすいですね)
②生産性を上げることが販売増につながる
③在庫が減り、PLだけでなくBSの改善につながる
④改善する意識が会社の組織競争力を高める
⑤製造で付加価値を生み出す
⑥組織競争力が高まり、現場で付加価値を生み出すことで、戦略を実行できるようになり業績向上につながる
②生産性を上げることが販売増につながる
「生産性が上がれば人経費を削減できる」これは普通に思いつきますが、「販売増につながる」これ、イメージわかない人もいるかもしれません
生産性が向上すると、日々の計画通り生産ができる工場になります
生産性の悪い工場は、ロスが多い
⇒ロスが多いと生産が遅れ遅れになる
⇒遅れると出荷計画に間に合わない
このようなことが繰り返されると、お客さんとの信頼関係を失いますね
ひどい会社になると、出荷計画を意識せずに生産している場合あるくらいです
「生産性向上活動の目的:出荷計画を守る」
この考え方重要です
そして、お客様/お得意様との信頼関係を構築することで、販売が伸びていくことにつながります
②在庫が減り、PLだけでなくBSの改善につながる(収支だけでなく現金が増える)
生産性の改善は在庫の削減につながります
在庫が削減されないと生産性は改善できないと言っていいかもしれません
(正しくは「削減」ではなく「適切な量」ですが)

在庫が減ると会社の現金が増えます
会社の現金が増えると投資がしやすくなります
販売規模の拡大もしやすくなります
業績につながるってわけです
④改善する意識が会社の組織競争力を高める
会社をや事業を成長させるには、戦略も重要ですが、戦略を実行する現場の組織としての能力も重要です
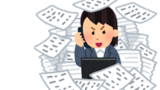
でも、組織は「維持する能力」はあっても「改善し続ける能力」は経営の強い意志がないと向上しません(トヨタはそれがカルチャーとなり当たり前になっている)
さらに、組織能力は個人だけ頑張っても向上しません
会社全体の活動として取り組む必要があり、定着するには非常にエネルギーと手間がかかります
そして、生産性向上の取り組みは、生産現場だけではできません
調達、販売、開発、商品企画、品質、生産技術、人事あらゆる部門が連携すること成果が出ます
そうすることで、各部門にも改善する意識が生まれ、それはその組織の能力の向上につながり、会社全体のレベルアップにつながります
結果として業績向上につながります
⑤製造で付加価値を生み出す
製造は元々、材料・部品を製品にすることで付加価値を生み出す部門ではあります
しかし、改善意識の強い製造は、それだけにとどまらず、より高い付加価値を生み出すことができます
商品企画や、開発、さらにはお客さんから難しい商品仕様の要求があっても、製造部門の能力/技術力不足で生産できない、できても高コストになる場合があります
しかし、製造部門そのものに改善する意識や能力があれば、皆で知恵を出し合い、その問題を解決しいい商品を生み出すことができるのです
「いい商品」=「新しい価値が載った商品」
ということです
それには、開発や商品企画だけでなく、製造の力も重要です
これは、どの部門も改善する力により、付加価値を生み出し会社の業績に貢献するの同じで、製造に限った話ではありません
⑥組織競争力が高まり、現場で付加価値を生み出すことで、戦略が実行できるようになり、業績向上につながる
これは、今までの話のまとめです
ご理解いただけると嬉しいです
まとめ
製造現場の生産性向上の改善活動をする意義、目的について考えてきました
効率的に生産するだけでなく、会社全体の組織能力を高めるために行います
・生産性を上げることが販売増につながる
・在庫が減り、PLだけでなくBSの改善につながる
・改善する意識が会社の組織競争力を高める
・製造で付加価値を生み出す
これらができることにより、最終的に
組織競争力が高まり、現場で付加価値を生み出すことで、戦略を実行できるようになり業績向上につながる
いかがでしょうか
皆さんのお考えも聞かせていただきたいと思います




コメント